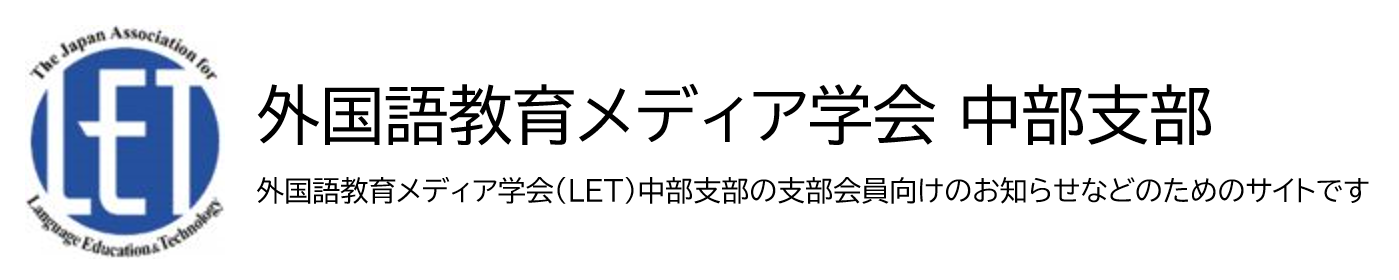卒業論文・修士論文発表
第1室(502室)
① 12:50-13:20
CLIL(内容言語統合型学習)実践授業における子どもの内容への興味:他教科(社会)の視点から
- 松原惇文(大阪教育大学学生)
発表種別
- 卒業論文発表
発表概要
CLILとは,Content and Language Integrated Learningの略称である。(以下,CLIL)。CLILとは,教科科目などの内容とことば(目標言語)を統合した学習を意味する。本研究では,外国語活動における子どもの内容への興味・理解はCLILの授業を実践することによって深まるのかどうか,授業実践を通して他教科の視点から検討することにした。
配布資料
- なし
② 13:25-13:55
音読・シャドーイングは4技能統合に有効か
- 杉山友希(南山大学学生)
発表種別
- 卒業論文発表
発表概要
2013年の学習指導要領改訂により、日本の中学・高校で行われる英語教育は従来の文法・訳読中心の指導から、コミュニケーション能力の育成そして4技能(聞く、読む、話す、書く)の統合を重視した指導へと転換した。そこで、音読やシャドーイングが教室で手軽に行うことができ、4技能統合に効果がある指導法としてますます注目を集めるようになってきている。 本研究では、先行研究のレビューに基づき、音読やシャドーイングが4技能統合に効果があるのか考察する。レビューの結果、音読は読解、シャドーイングは聴解およびスピーキングにそれぞれ効果があることが明らかになった。また、音読・シャドーイングは熟達度低い学習者が苦手とする音韻符号化を促進する働きがあるため、熟達度が低い学習者の言語学習を容易にする可能性が示唆された。しかし、それぞれ単独で4技能統合に効果があるとはいえず、他の指導法と組み合わせて使用する必要がある。
配布資料
- なし
③ 14:00-14:30
フォーカス・オン・フォームを取り入れた小学校英語:Teacher Talk, Teacher-Childの発話分析から
- 半田智彦(大阪教育大学学生)
発表種別
- 卒業論文発表
発表概要
教師が授業内で使用するteacher talkが学習者である子ども達にどのような影響を与えるのか, ということの研究を行った。その為に, (1)英語を学習する子ども達がteacher talkをどれくらい理解できているのか, (2)子ども達はteacher talkを授業内容理解に役立てることができているのか, という2 点を, CLILを用いた実践授業を行うことを通して考察していく。方法として、I. 良いteacher talkが使用されている授業の分析について, CLIL(Content and Language Integrated Learning内容言語統合型学習)の第1人者であるイタリア,ピネローロ市立シルコロ小学校で英語指導を担当されているシルヴァナ・ランポーネ氏(Ms. Silvana Rampone)の「フルーツ」の授業を訪問観察し, 分析(ディスコース分析)を行い, 使用されているteacher talkを見本として捉えていく。II. 小学校での筆者の授業実践後のアンケート分析について, N市立K小学校6年生35名に授業させて頂いた「経済(流通)」に関する筆者の授業分析, 子どもの対話, アンケート分析を行い、その結果を考察していく。
配布資料
- なし
④ 14:35-15:05
協同学習を取り入れた英語リーディング授業:学習者の意識および動機づけへの影響
- 山田秀子(名古屋学院大学大学院生)
発表種別
- 修士論文発表
発表概要
主体的・能動的な学びの重要性が注目されるなか、小グループでの学び合いによる協同学習に期待が高まっている。本研究では、専門学校生46名を対象に協同学習を取り入れた英語リーディング授業を計画・実践し、学習者の協同学習に対する意識および学習の動機付けへの影響を調査した。授業実践開始前と終了後に質問紙調査を実施し、その後4名に面接を行った。その結果、学生は協同学習を概ね肯定的に捉え、協同的な学びは学習内容の深い理解、知識構築、対人スキルの向上において効果があると認識する傾向が高いことが示された。一方で、講義の利点も認め、協同学習と講義の両方を取り入れた授業が好ましいと考える学生が多いこともわかった。動機付けへの影響については全般的に肯定的な結果が示され、内発的動機付けが有意に高まった。外発的動機付けは英語習熟度によって異なる傾向がみられ、その一因としてグループの成員が均質であったことが考えられる。
配布資料
- なし
⑤ 15:10-15:40
CLIL授業における子どもの言語面での学びと思考:授業におけるディスコース分析をとおして
- 中村愛(大阪教育大学大学院生)
発表種別
- 修士論文発表
発表概要
コミュニケーション能力の育成を進捗し,児童が内容に興味を持ち満足できるような教授法として,内容言語統合型学習(CLIL:Content and Language Integrated Learning)に注目する。本研究では海外と日本の計4カ国の公立小学校にてフォーカス・オン・フォーム(Focus on Form: FonF)を取り入れたCLILの授業実践を行い,その際の英語の理解度・思考・発話についてまとめ,思考と言語の絡み合わせ(intertwine)の場面を見極め,小学校の年齢におけるCLILの可能性と日本での応用を探ることを目的とした。ディスコース分析から,ベテラン教員のティーチャートークや児童の発話から思考の分類を行った。アンケートでは理科CLILで扱った語彙の理解度クイズを行い,背景の異なる3校(X, Y, Z)を一元分散分析で比較すると有意差がないことが分かり,英語の習熟度にあまり影響されず,教科特有の語彙を理解していたといえる。教材やティーチャートークの工夫をすれば,CLILの日本の小学校への応用で気を付けることが示唆された。
配布資料
- なし
第2室(515室)
① 12:50-13:20
英語教育における翻訳評価の再考:“a young girl” は「少女」か?
- 守田智裕(広島大学大学院生)
発表種別
- 修士論文発表
発表概要
日本の英語教育における「訳」は、辞書や文法書等を用いて訳出する 「英文和訳(置換え訳)」と,原著の発話者 の心身状況 を考慮して原典で理解した内容を日本語で再表現する「翻訳」に分類される。「英文和訳」の評価は従来、原典との正確さを観点に点数化されるが、後者の「翻訳」は必ずしも客観的な点数化を必要としないのではないか。 それに対する代替案 として、本発表はArendtの議論を援用した複数名の他者 による質的評価の例を提示する。 協力者は学部生1名と翻訳経験者2名で、学部生が物語文を訳出した際の文章と訳出プロセスに関する語りを、翻訳経験者2名に提示して評価を依頼した。その結果、学部生が “a young girl” という名詞句を「少女」と訳出した際に、その人物像や他の登場人物との人間関係を考慮していたが、翻訳経験者2名がそれぞれ異なる観点 (自然さ・物語のミステリー性) から「少女」という訳の問題点を指摘したことが分かった。
配布資料
- なし
② 13:25-13:55
高校生におけるCLIL授業実践と英語力向上について:オーストラリア語学研修をとおして
- 森下祐美子(大阪教育大学大学院生)
発表種別
- 修士論文発表
発表概要
CLILとは,「教科を語学教育の方法により学ぶことによって効率的かつ深いレベルで修得し, 英語を学習手段として使うことによって実践力を伸ばす教育法」である(渡部他,2011)。以下4点を研究目的とする。オーストラリアでCLIL実践授業を主体的に生徒が行うことが, (1)英語力に変容が見られるのか, (2)その変容が生徒の情意面や「書く力」につながるのか, また, 日本でCLIL実践授業を主体的に生徒が行うことが, (3)英語力に変容が見られるか, (4)その変容が生徒の情意面や「書く力」につながるのか, 検証する。実践(1)では, 日本の高校2年生がオーストラリアの高校2年生にCLIL(理科物理:表面張力分野)の授業を行ったグループ(CLIL群, N=13)と, 行わなかったグループ(Non-CLIL群, N=25)における事前・事後の英語力・情意面・「書く力」がどう変容したか, (1)英語学力テストにおける比較, (2)英語ライティングの質的変容を観察し, (3)質問紙調査分析を行った。実践(2)では, 日本の高校2年生が日本の生徒にCLIL(理科物理:屈折分野)の授業を行い, CLIL群(N=78)とNon-CLIL群(N=72) における事前・事後の英語力・情意面・「書く力」がどう変容したか, (1)英語学力テストにおける比較, (2)英語ライティングの質的変容を観察し, (3)質問紙調査分析を行った。それぞれのCLIL実践に関する一連の結果を発表で報告する。
配布資料
- なし
③ 14:00-14:30
現在完了の使用法
- 渋谷茉由(三重大学学生)
発表種別
- 卒業論文発表
発表概要
私の論文では,現在完了が持つ意味合いを明確化すると共に,中学生の英語力の水準に沿ったその導入方法を提案する。第1章では,現在完了の本質を,「現在との関連をもつ過去の出来事や状態を表すもの」として取り上げる。そしてその意味合いを「経験」,「結果」,「継続」の3つの用法に区分し,日本語話者が混同しがちな「過去形」と比較しながらそれらの特徴を捉える。第2章では,中学校で使用される6つの教科書の用法の導入順序,それぞれの用法を表した図,用いられている例文を示す。そして説明に用いられている図や例文で用いられている動詞,3つの用法についての説明の仕方などについて考察する。第3章では,現在完了の本質の理解を促す問題や現在完了と過去形の違いの導入方法に加え,現在完了と共に使われる頻出の副詞 (twice,already,since など) についても触れる。そしてまとめとして,現在完了を扱う上で,3つの用法について,学習者の理解を促す指導順序を提案する。
配布資料
- なし
④ 14:35-15:05
小学校英語教科化に向けた中学年の指導の在り方:児童の発達段階に着目して
- 早川空(大阪教育大学学生)
発表種別
- 卒業論文発表
発表概要
小学校英語が教科化するに伴い,中学年から英語の授業を始めた場合の指導の仕方や発達段階に応じた指導の仕方を考える。先行研究では発達段階について様々な論文を読み中学年の発達段階について考える。またアンケートやインタビューを実施し様々な教員や教育委員会の方の意見を問う。そして自身が実際に小学校へ赴き中学年に向けた授業を実践する。以上より考えたことや感じたことを発表する。
配布資料
- なし
⑤ 15:10-15:40
日本人EFL学習者の英文法理解に必要な要素 :言語分析能力(L1/L2)との相関からみる分析
- 中村光揮(静岡大学大学院生)
発表種別
- 修士論文発表
発表概要
言語適性と呼ばれる言語分析能力は、他の2つの能力(音韻的能力と記憶力)に比べて、どの学習段階においても学習効果に大きな影響を与える重要な要素だとされているが、具体的にどういった能力で、言語のどんな側面(統語構造や機能)と関連した能力であるのかは明らかにされていない。そこで、言語分析能力がL1とL2で関連した能力であるのか、どういった文法項目に影響を与える能力であるのかを実験した。日本人英語学習者の大学生78人に対して、日本語、英語の言語分析能力テストと英語の文法理解テストを5つの文法項目をターゲットにして実施し、相関分析と分散分析を使って各テストの関係性と回答の傾向を調べた。日本語と英語の言語分析能力には相関がみられたが、同文法ターゲットごとよりも、異なったターゲット同士のほうがより強い相関があった。文法理解テストと言語分析能力テストの得点のばらつきを分散分析でみてみると、言語分析能力テストは文法項目ごとに共通した得点傾向がみられたが、文法理解テストにはみられなかった。
配布資料
- なし
第3室(516室)
① 12:50-13:20
Elementary School English Education in Japan and Other Countries
- 荒木麻由(仁愛大学学生)
発表種別
- 卒業論文発表
発表概要
I am interested in elementary school English education, and I would like to know the differences of educational systems between Japan and other countries. Therefore, I searched about them, and discussed Japanese elementary school English education. Through writing this thesis, I could know the present situation. We have a lot of things to think about elementary school English education. For example, class hours, teacher training, continuity from elementary school to junior high school. Therefore, I would like to tell about elementary school English education, and I want everyone to think about it more through my presentation and the thesis.
配布資料
- なし
② 13:25-13:55
Effects of Negotiation of Meaning on Lexical Acquisition in Computer-Mediated Communication
- 張紅旭(名古屋大学大学院生)
発表種別
- 修士論文発表
発表概要
The study investigated the effect of negotiation of meaning among sixteen Japanese EFL learners on their lexical acquisition in computer-mediated communication, especially focusing on the differential learning processes that participants engage in during a single negotiation routine and detailed analysis of text data basing on NNS-NNS negotiation model (Varonis & Gass, 1985). With more than 2/3 words being negotiated and participants making significant progress in lexical acquisition, the result can be interpreted as supportive for the Interaction Hypothesis (Long, 1996). The comparison between interaction and list-provided interaction learning suggested that both processes facilitate lexical acquisition, with list-provided interaction especially helpful in retention of word recognition. Text data revealed massive usage of rephrasing, expansion and deduction testing, which allowed learners to acquire more comprehensible input facilitating acquisition. The data also revealed preemptive input interaction and the usage of keyboard symbol, which can be seen as the exclusive features of computer-mediated negotiation.
配布資料
- なし
③ 14:00-14:30
Examining Japanese Teachers’ Use of L1 in English Classes: Frequency, Function and Reasons behind them
- 泉谷忠至(奈良教育大学大学院生)
発表種別
- 修士論文発表
発表概要
Senior high school teachers are supposed to conduct English classes mainly in English, and junior high school English classes will be also taught mainly in English (MEXT, 2013). However, Japanese should not be excluded in lessons (Sato, 2015). This study researched Japanese English teachers’ use of L1. In the study, lessons by one senior high school teacher and two junior high school teachers were recorded and transcribed to calculate the frequency and function of their L1 use. After the lessons, stimulated recall interviews and questionnaire surveys were conducted to examine the reasons of their L1 use. The result showed that there was a difference in their L2 use in lessons among the teachers whose language proficiency levels were almost the same, and that the most frequently used function of L1 use in the three lessons was activity instruction, followed by explanation and translation. In the presentation, more detailed analysis of the result will be reported.
配布資料
- なし
④ 14:35-15:05
第二言語語彙習得における受容的・産出的検索練習の効果:英語疑似単語と手の動きの組み合わせの学習に関して
- 柳沢明文(信州大学学生)
発表種別
- 修士論文発表
発表概要
発表者は先行研究Yanagisawa (in press)で、イラストと組み合わされた擬似英単語の学習における検索の効果を検討した。本研究では、その追研究として、未習の意味を持った語彙学習における検索方法の違いが英語の疑似単語の学習に与える影響を明らかにすることを目的に行われた。参加者に(1)形式から意味を想起する練習の機会のある条件、(2)意味から形式を想起する練習の機会のある条件、(3)想起練習の機会のない条件、という3条件で、手の動きを組み合わされた擬似英単語を学習してもらった。単語の受容語彙と産出語彙が測定された。受容語彙には受容検索が効果的だが産出検索は効果的ではなく、産出語彙には産出検索が有効であったが、受容検索は効果的ではなかった。結果や先行研究との違いの理由について考察を行った。
配布資料
- なし
⑤ 15:10-15:40
理学療法士を調査対象にしたESPニーズ分析:調査結果を養成校の英語教育につなげるために
- 小林信子(名古屋学院大学大学院生)
発表種別
- 修士論文発表
発表概要
臨床理学療法士を対象にESPニーズ分析を試みた。調査にはアンケート調査・聞取り・ヒアリングを三段階で用いた。質問紙は回答を多面的にとらえるため4種のニーズ概念につき10種のタスクを立てて5件法で答える方式とした。先行研究との比較では, 結果が合致するもの・しないものの間で度数に有意の差がみられた。新たにニーズが生じたタクス, 職場が医療系か福祉系かで慎重な分析を要するタスクもあった。こうした差は, 対象を理学療法士に絞った点に加え, 時代変化と情報手段の発達が影響していると考えられる。養成校の多くで医療英語と一般英語が必修科目とされる中, 授業評価で差が示され, 各担当教員が協力し相互に補完し合うシラバスの作成が望ましい。また今回は愛知県を調査地としたが, 今後の調査では養成校の所在地や種別により英語科目の履修期間や内容にバラつきが予測される。川越(2001)が示唆する, 医療専門職全体と個別職域のニーズ分析を系統的に行うことができる調査手法の確立と研究の連携が望まれる。
配布資料
- なし
第4室(517室)
① 12:50-13:20
PPPやTBLTで日本の中学生に英文法を教える方法
- 石橋征典(三重大学学生)
発表種別
- 卒業論文発表
発表概要
私の論文では、[PPP (Presentation Practice and Production)とTBLT (Task-Based Language Teaching)という2つの教授法について比較する。そして、それぞれの教授法の良い点や悪い点を指摘しながら、英語教師が、中学生に英語でコミュニケーションをとることのできる力を身に着けさせる方法を提案していく。また、同時に中学生が文法を身に着けることの重要性について確認する。第1章では、PPPを説明→練習→活動の3つに分けて、中学生が英語における4技能(話す、書く、聞く、読む)の力を伸ばすための指導方法や指導上の留意点及びPPPの長所や短所について考察する。第2章では、TBLTをプレタスク→タスクサイクル→事後指導の3つに分けて、第1章と同様に、指導方法や指導上の留意点及び、TBLTの長所や短所について考察したり、適切なタスク活動の選び方について述べたりする。第3章では、第1章や第2章で述べたことを基にして、それぞれの教授法の問題点を改善した指導案をPPPバージョンとTBLTバージョンの2つ作成する。指導案では、比較表現を扱う。
配布資料
- なし
② 13:25-13:55
小学校外国語活動で生きるティーム・ティーチングの在り方:HRTとALTへのインタビュー分析を中心に
- 千足奈津紀(大阪教育大学学生)
発表種別
- 卒業論文発表
発表概要
本研究では,まず,ティーム・ティーチングの必要性や課題について考察し,現在のティーム・ティーチングがどのように行われ,どのような課題を抱えているのかを整理する。次に,担任・ALTへ半構造化インタビューを行い,現場の先生がティーム・ティーチングをどのように捉えているのか,互いの課題を聞き,ティーム・ティーチングが有効な授業例を考察する。上記の研究をもとに,研究授業を行い,子どもが抱える課題や教員間の課題,またティーム・ティーチングの有効な授業を考察する。
配布資料
- なし
③ 14:00-14:30
- なし
④ 14:35-15:05
- なし
⑤ 15:10-15:40
- なし