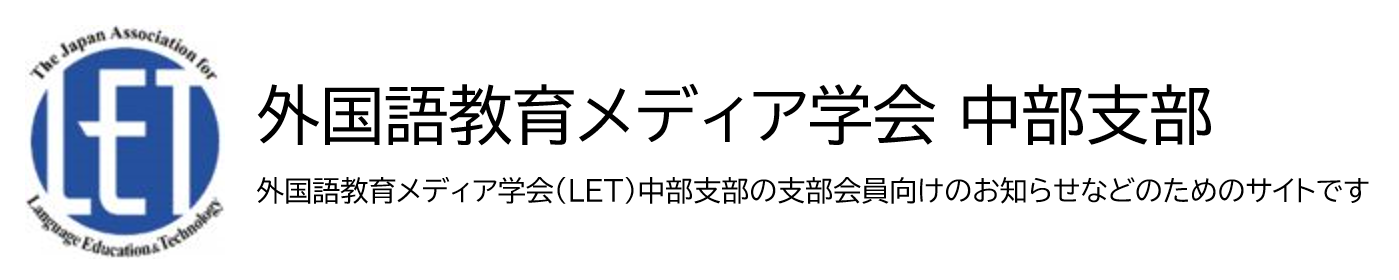基調講演
外国語学習の動機づけを探る:動機づけ要員、動機づけ方略、情意要因との関係を通して
- 講師:竹内理(関西大学)
発表概要
本講演では、冒頭で、講演者のこれまでの研究活動の流れを振り返り、なぜ今回、このテーマを選んだかを説明する。その後、動機づけ研究の外国語(英語)教育学における重要性を、2020年実施の教育改革との関連で説明する。続いて、講演者らの様々な研究をもとに、教室「外」での学びの重要性について言及し、その過程に影響を与える動機づけ要因に関しても概観する。これとの関連で、学習者が、動機づけ要因をどう捉え、知覚しているかについての研究も紹介していく。次に、視点を教員側に移し、学習者の動機づけへの教員の働きかけ(つまり動機づけ方略)に関する研究成果に触れる。また、動機づけとその他の情意要因(学習不安、自己効力感など)、そしてL2 習得との関係に、質・量の両面からアプローチした研究を紹介し、今後の外国語教育研究のあり方(たとえば、関心相関性や共約可能性の導入)について述べる。最後に、これから研究を続けていく若手研究者に向けて、トレンドを起こすことの重要性に関して言及し、講演を締めくくる。
配布資料
- なし
シンポジウム
若手研究者が考える四技能指導の理論と実践
- コーディネーター:石井雄隆(早稲田大学)
- パネリスト
- 長谷川佑介(上越教育大学):リーディングの観点から
- ”リサイクル”を意識したリーディング授業の設計図
- 山内優佳(広島文化学園大学):リスニングの観点から
- 課題の発見ができる学習者の育成を目指した英語リスニング指導
- 福田純也(静岡県立大学):スピーキングの観点から
- タスクを用いた英語スピーキング授業の実践
- 川口勇作(名古屋大学大学院生):ライティングの観点から
- 学習支援システム上でのフォーラムライティングの実践事例
- 長谷川佑介(上越教育大学):リーディングの観点から
- 提供:リアリーイングリッシュ株式会社
趣旨
英語教育における四技能の指導の在り方について、近年盛んに議論されています。本シンポジウムの趣旨は、四技能それぞれの分野の研究をされており、大学の英語教育に関わり始めたばかりの若手の先生方に英語の授業の実践例をお話しいただきます。その中で、実践の根拠となる理論にも触れていただくことで、実践を組み立てるためのヒントを参加者と共有し、望ましい四技能の指導の在り方について議論できればと考えています。
”リサイクル”を意識したリーディング授業の設計図
- 長谷川佑介(上越教育大学)
発表概要
英語で授業を進めることが基本とされている現在でも、大学生の多くが文法訳読型の英語授業を高校時代までに経験している。しかし、「英語リーディング=英文の和訳作業」という固定観念を抱かせたまま彼らを社会に送り出してしまうわけにはいかない。特に勤務校のような教員養成大学にあっては、多様な授業方法を体験させることで学生の視野を広げさせる必要がある。私の英語リーディング授業では、予習は一切させず、授業中にも和訳作業は行わない。教師が行う説明の時間を可能な限り減らし、その代わりに英文素材を繰り返し利用する(リサイクルする)ことで、読みにかける時間を出来るかぎり増やしている。また、大学ではあまり実践されていないと思われる音読活動も積極的に取り入れている。本発表は、出来るかぎり理論的な背景や実証研究からの示唆と関連づけながら、日ごろ実践している取り組みを紹介して忌憚のない意見を乞うものである。
配布資料
- なし
課題の発見ができる学習者の育成を目指した英語リスニング指導
- 山内優佳(広島文化学園大学)
発表概要
現在,「確かな学力」や「アクティブ・ラーニング」といったキーワードの下で,学習者が自ら課題を見つけ,解決に向かって能動的に学習することが重要視されています。しかしながら,リスニングは音声言語を扱うその性質上,学習者自身がリスニング上の課題を明らかにすることは難しいといえます。発表者の実践においては,種々の活動(大まかな内容理解→キーワードの聞き取り→日本語訳による意味理解→ディクテーション等による聞き取り)それぞれにおいて,注目すべきリスニングの下位技能を学習者に伝えています。また,リスニング中に課題(つまずき)が生じるよう,やや難易度が高い教材を使用するようにしています。「難しい」から「こうしたら理解できるようになった」への過程を授業内で積み重ねることが,授業外においても学習できるアクティブ・ラーナーの育成につながると考えています。
配布資料
- なし
タスクを用いた英語スピーキング授業の実践
- 福田純也(静岡県立大学)
発表概要
本発表では,発表者の勤務校で行った,タスクを用いた英語スピーキング授業の実践について報告する。まず,授業を実践するにあたり事前に設定する目的・目標および評価方法を,どのような観点から考慮し,その目標に到達するためにどのように教育的タスクを配列したのかを報告する。その際には,実践の根拠となる「タスクを用いた言語指導法(task-based language teaching)」の理念を説明し,その理念が,先行研究において実践にどのような示唆を与えるといわれてきたかを示しつつ,実践に導入する際に発表者が役立ったと感じた,もしくは困難を感じた点について述べる。そののち,授業開始時からはどのような点に留意し,変更を行いながら授業の実践を進めたかについて,学生の様子を述べながら報告する。
配布資料
- なし
学習支援システム上でのフォーラムライティングの実践事例
- 川口勇作(名古屋大学大学院生)
発表概要
報告者は、国立大学の1年生を対象とした英語コミュニケーションの授業で、授業外の学習活動として学習支援システム上のフォーラム(掲示板)でのライティング活動を実施している。フォーラムライティングは非同期的コミュニケーション手段であり、チャットなどの同期的コミュニケーションと比較して、プランニングや推敲の時間が十分に取りやすく、また書き込む前に他の学習者が書いた内容を参照できるため、他の学習者の文章スタイルや表現などを参考にすることができる、といった利点がある。本報告では、今回の実践の詳細や、実践上の課題を紹介した上で、学習者のライティングに対する不安などを中心とした、ライティングに対する意識の変化に着目した観察の展望を報告する。
配布資料
- なし
ワークショップ
認知科学化した外国語教育研究とその後の方向性
- 講師:草薙邦広(広島大学)
概要
外国語教育研究の歴史を眺めてみると,その時々において,数多くの研究者があるひとつの方向へ一斉になびくことが何度かありました。1990年代から昨今に続く大きな流れのひとつは,認知主義(cognitivism)とよばれるアプローチで,この時代の研究における主翼でした。ですが,昨今に至り,この認知主義はさまざまな批判を受けるようになりました。さらに,2010年以降では,(a)社会構築主義,ポスト認知主義,複雑系,そして創発主義の台頭,(b)統計改革,再現可能性問題,そして統計手法の高度化,(c)エビデンスにもとづく教育政策,(d)学力観・熟達度観の変遷,といった複雑な動きが見られ,我々の方向性は,ますます見渡しにくくなっています。
そこで,本ワークショップでは,講師による話題提供の後,外国語教育研究の今後のあり方,そして参加者自身のアプローチについて,グループワーク形式で活発な意見交換を行い,さらにグループ内の意見を全体でまとめて発表してもらいます。日頃,研究の哲学的な部分について議論を行えないご多忙な先生方,研究のあり方に漠然とした悩みを感じる院生・学部生,そして研究アプローチに関心のあるすべての方々の参加をお待ちしております。
配布資料
- なし
研究発表
① 14:45-15:15
The Implementation of the Peer-review Activity Focusing on 5W1H Questions: An Approach to Improving Students’ Writing Performance
- 辻香代(立命館大学)
発表概要
This presentation describes a pilot study that investigated the effects of peer-review activity, focusing on 5W1H communicative questions, on students’ writing performance. The participants of this study were 14 sophomores at a large private university in western Japan. The instructor conducted three types of teacher interventions: 1) instructions on what to discuss and how to organize their arguments in each section. 2) Instruction and explanation of how to conduct the 5W1H activity. 3) Demonstration of the activity. The activities were done in a pair or a group setting. The participants were provided with 5W1H worksheets in which the key consideration for the activity was summarized. To evaluate the process, the instructor and one independent rater assessed participants’ texts prior to and post 5W1H process, using the writing rubric constructed for this study. The results showed that the process had positive influences on students’ texts. The revisions leading to a better text became clearer with newly modified 5W1H information. The activity renewed students’ focus on the importance of clearly describing 5W1H elements of an information. Therefore, it can thus be concluded that the process did enhance students’writing performance.
配布資料
- なし
② 15:20-15:50
言語リズム類型論の変遷と第二言語リズムの測定
- 天野修一(静岡大学)
発表概要
様々な指標を用いて第一言語と第二言語の発話リズムを比較しようをする研究が、2000年代以降、間断なく発表されている(e.g., Grenon & White, 2008; Kinoshita & Sheppard, 2011; Lai, Evanini, & Zechner, 2013; White & Mattys, 2007a; 2007b)。このような研究は、言語のリズムを強勢拍リズムと音節拍リズムの二分法で理解しようとした類型研究を起源とするが、リズム指標の研究が高度化する中で、そのような研究がいかなる経緯で第二言語のリズムを分析する指標の研究に結びついたのかについては関心が薄れ、誰もが理解しているとは限らない。そこで本発表では、1940年代頃から2000年代頃の言語リズム類型論の文献を検討し、その変遷を整理することを通じて、第二言語リズムの研究との関係を示す。
配布資料
- なし