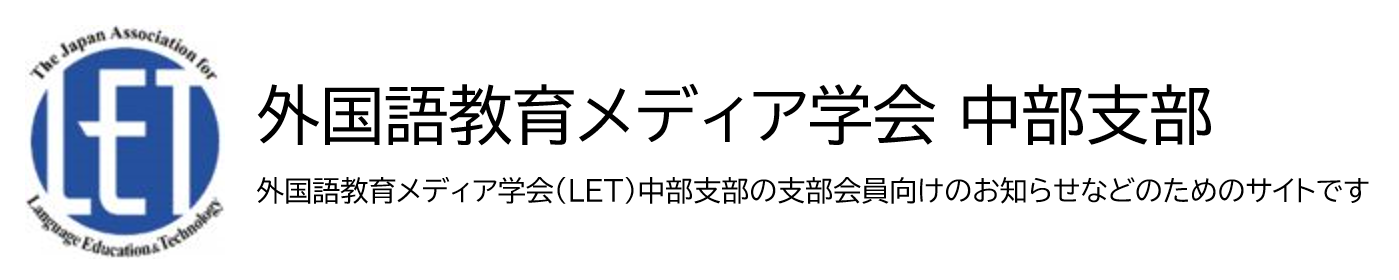基調講演
言語の可視化をめぐって:こころと言葉の交響
- 講師:石川慎一郎(神戸大学)
講演概要
先日,あるサイト上で自分自身が「第2言語習得論の研究者」と紹介されていることを知った。自分ではそのように考えたことはただの一度もなかったので,ずいぶん驚いたのだが,一般に,研究者には何らかのラベルが張られることが多い。「**の研究者」「**の紹介者」「**の大家」といったものである。では,私なら自分自身にどんなラベルを張るか考えてみるのだがこれが意外に難しい。
私の卒業論文のテーマは「ディラン=トマス詩論:初期詩群におけるヴィジョン・メイキングの過程の一考察」であった。先般,ノーベル文学賞を受賞したボブ=ディランの名前の由来にもなったトマスの詩は,初めて読むと,何のことを言っているのかまったくわからない。しかし,英語があまり読めない東洋の若造でも,トマスの言葉が暴力的なエネルギーを持っていることだけは即時に理解できた。
トマスの詩に限らず,言葉には,意味がわからないのにこころだけは確実に伝わる,といったことがよく起こる。そんな不思議なことがなぜ起こるのか,これが私の抱いた最初の疑問だった。あるテクストについての「なぜ」を説明するには,そのテクストの外の言葉や枠組みを使う必要がある。学生時代の私は,主に2つの枠組みで問題を考えるようになった。1つは当時の哲学界を風靡していたフランス発のディコンストラクション理論で,もう1つは言語学,とくに文体論や機能文法などの枠組みである。ディコンストラクションでは,テクストを自立的にとらえ,テクストの意図をテクスト自身が裏切る(脱構築する)メカニズムに着目する。文体論では言語がある特定の効果を生じる仕組みの解明を目指す。文学の先生と哲学の先生と言語学の先生に同時に師事するという,今ではあまり見られない融通無碍な学生生活を送りながら,目に見えない言葉の機能を可視化する,というテーマにずっと向き合ってきた。その後,研究者になり,心理言語学の各種の実験手法や,脳機能測定,また,コーパス分析など,「なぜ」に接近する道具立てはいろいろ変わってきたが,問いそのものは今も昔も変わらない。それは私にとっていつまでも提出できない「宿題」のようなものである。
目をつぶっていると神様が見えた/うす目をあいたら神様は見えなくなった/はっきりと目をあいて神様は見えるか見えないか/それが宿題(谷川俊太郎「神様」『これが私の優しさです』所収)
若手キャリアパス座談会
全体概要
この座談会では,若手の学校教員・大学教員の先生方と大学院生で,若手のキャリアパスについて議論します。「若手」と言っても,「年齢が若い」ということではなく,「外国語教育の分野において,教育や研究のキャリアがまだ浅い人たち」ということを意味しています。そうした中でも,現在院生の立場にいる方とキャリアはまだ浅いけれども学校教員や大学教員として勤務している先生方をお呼びし,外国語教育に携わる若手のキャリアパスを考えていきたいと思います。 現在大学院に在学している方のみならず,「大学院への進学を考えているけれど,進学後の就職について悩んでる…」という学部生の方や,「博士後期課程に進学しようかと考えているけれど,研究者としてやっていけるのだろうか…」という修士課程院生の方はぜひご参加ください。 もちろん,院生や学部生の指導生をお持ちの先生方や中学・高校で教壇に立たれている先生方,大学院生のキャリアパスに興味がおありの方など,たくさんの方のご参加をお待ちしております。
学校教員志望の部
- 司会:石井雄隆(早稲田大学)
- 登壇者
- 福田朱莉(岡崎市立矢作北中学校)
- 押見奈美(愛知教育大学大学院生)
概要
英語教育を巡っては,英語コアカリキュラムの策定や2020年大学入試改革など様々な改革が現在進められています。若手キャリアパス座談会 「学校教員志望の部」では,英語教育を巡る社会的状況を踏まえながら,現職の中学校の先生と教員志望の大学院生をお招きし,「院生時代に思っていたことと勤務して分かったことのギャップ」,「教員になった後,自分が大学院で行った研究やその他の活動で教員の仕事に生かされている部分」などの共有を通しながら,若手のうちに身に着けておくべきスキル・知識・人間関係や大学院進学の意義の共有などについてフロアと一緒に議論し,明日の英語教育について考えていきたいと思います。
資料
大学教員志望の部
- 司会:田村祐(名古屋大学大学院生)
- 登壇者
- 草薙邦広(広島大学)
- 名畑目真吾(共栄大学)
- 梅木璃子(広島大学)
概要
大学教員としての就職を目指す若手にとって,大学教育改革にともなう大学教員の雇用形態の多様化はますます無視できなくなってきています。しかしながら,実際にどのようなポジションがあり,それぞれのどのような役割を担っているのかをうかがい知ることができる機会はあまり多くありません。そこで,「大学教員志望の部」では,まずこうした多様な雇用形態を踏まえた上で,どのようなポジションにはどのようなキャリアがありうるのかを考えていきます。また,「就職前にどのようなスキルや知識を身に着けておくべきだったか」,「実際に就職してみてわかった大学教員の仕事」,「若手支援の取り組みの必要性」などの話題を通じて,フロアと一緒に外国語教育研究の今後について考えを深めていきたいと思います。
資料
研究発表
① 14:00-14:30
英語母語話者及び日本人学習者の英語発話における非流暢さの比較
- 小林真実(名古屋大学大学院生)
発表概要
本研究の目的は,英語母語話者と日本人学習者の英語スピーキングにおける非流暢さの発 生箇所を検証することである。NICT JLEコーパスを使用し,母語話者及び日本人学習者の発話における無音及び有音ポーズ,言い直し,同じ単語の繰り返し,談話標識 (well) が発生数を,節中,節間において比較した。その結果,ポーズは総発生数及び 4 つの発生箇所において,日本人学習者の発話では英語母語話者と比して多かった。言い直しは,総発生数は 日本人学習者が多かったが,接頭の言い直しは両群において同様であるのに対し,節中の言い直しは日本人学習者に多くみられた。同じ単語の繰り返しは,総発生数,接頭及び節中において日本人学習者が多かった。また,談話標識 (well) は,英語母語話者の発話では発生しているのに対し,日本人学習者の発話において殆どみられなかった。発表では,日本人学習者の英語スピーキングにおける困難点に関する示唆について報告する。
配布資料
- なし
② 14:30-15:00
「タスクの複雑さ」は認知的負荷を高めるか:学習者の主観的なタスクの困難度の観点から
- 岩谷真悠(名古屋大学大学院生)
発表概要
タスクが複雑になると,タスクの要求する認知的負荷が高まり,タスクの難易度が上がるとされている。多くのタスクの複雑さに関する研究では,研究者が理論的要因に従ってデザインした難易度の低い単純なタスクと難易度の高い複雑なタスクを学習者に課し,タスクを行った学習者の言語パフォーマンスに関する考察が論じられてきた。しかし,これらの手法では,タスクが実際に複雑であったかが確認できず,学習者の言語パフォーマンスに表れた特徴がタスクのデザインが要因であることを裏付ける証拠が不十分である。よって本研究では,タスクを行った学習者の自己評価による主観的なタスクの困難度を測定し,タスクが複雑になると学習者が実際に難しいと感じるのかどうかを検証した。分析の結果,単純なタスクと複雑なタスクにおける学習者のタスクの困難度の評価値を比較したところ,有意差はなかった。よって本研究結果からは,タスクの複雑さを操作しても,認知的負荷が高まっていない可能性が示唆された。
配布資料
- なし
③ 15:00-15:30
認知的アプローチに基づくパフォーマンス指標解釈の問題点:存在論的アプローチによる批判的検討
- 福田純也(静岡大学)
- 西村嘉人(名古屋大学大学院生)
- 田村祐(名古屋大学大学院生)
発表概要
本発表では,CAFの存在論的な実在性を問い直し,CAFはその成立背景から総括的モデルに属すが反映的モデルとして捉えられてきたという理論的な「ねじれ」を指摘する。そして近年の有力な見方のひとつとして複雑性理論の観点を取り上げ,CAFを複雑系から創発する表面的な現象と捉えることを試みる。そして,そのような観点から見て立ち現れる二つの問題点,すなわち(1)指標選択の恣意性に関する問題と,(2)テクスト情報と能力および認知プロセスの同一視に関わる問題を取り上げ議論する。これらの考察をもって,パフォーマンス分析から認知プロセスの特定を行うこと試みは,科学的知識の収束を阻害するといった根本的問題を持つことを指摘する。
配布資料
- なし