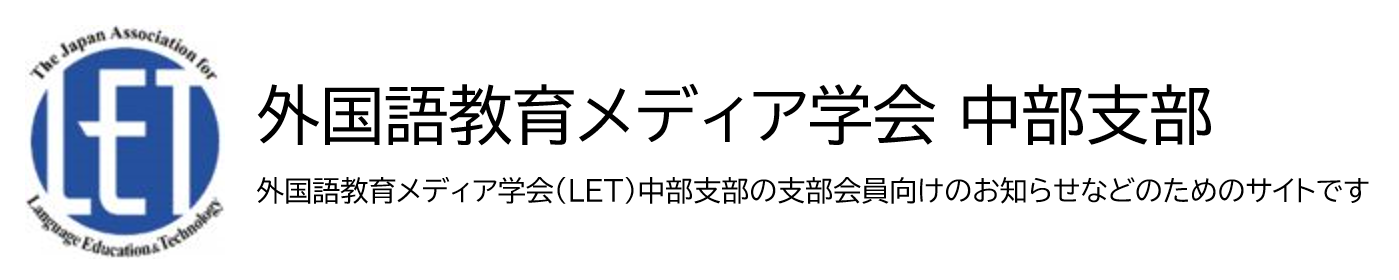講演①
量的データの分析・報告で気をつけたいこと
- 講師:水本篤(関西大学)
時間
- 11:00-12:00
会場
- ファカルティラウンジ
講演概要
外国語教育研究では,現在,量的データを用いた論文や発表が大半を占めていますが,その分析や報告では,再現性に乏しい不十分な方法が用いられていることがあります。今回の講演では,特に『英語教師のための教育データ分析入門』(前田・山森,2004)や『外国語教育研究ハンドブック』(竹内・水本,2012)に基づき,データの分析・報告における基本的な注意点や,その他の気をつけておきたいことについてお話します。
配布資料
配布資料はこちらからダウンロードできます。
講演②
外国語教育研究を実りあるものにするために:測定すること・整理すること・分析すること・解釈すること
- 講師:前田啓朗(広島大学)
時間
- 16:30-17:30
会場
- ファカルティラウンジ
講演概要
外国語教育に携わる私たちにとって,測定すること(成績評価やデータ収集など)・整理すること(データの電子化など)・分析すること(作図や統計処理など)・解釈すること(分析結果の吟味や意味づけなど)という手順は,指導においても研究においても,肝要なことといえます。これから教育・研究の道に進もうという立場から,すでにその道に入った立場の方々まで,当日の研究発表等をふまえて,これらの手順を振り返る機会になるようなお話をします。
ワークショップ1
文法指導ってなんなのさ:目的・内容・方法
講師:亘理陽一(静岡大学)
時間
- 15:40-17:10
会場
- ファカルティラウンジ
概要
本ワークショップでは,教育内容あるいは研究対象として文法指導・学習に関心のある方を対象として,外国語としての英語の文法指導の目的・内容・方法を論じます。予備知識や指導経験は特に必要ありません。文法にどういう側面があり,どういう順序で,どのような例文やどのような問いによって,その形式・意味・使用の教授・学習が可能となるのか,どのような記述と説明であれば知りたいと思うのかといったことを,諸学問の知見に依拠しながら,以下に関する具体例を通じて考えます。
- 可算性,冠詞,関係節
- 他動性,態,使役,比較
- 時制と相,ムードとモダリティ
配布資料
- www.slideshare.net
- docs.google.com
ワークショップ2
有益な情報を捨ててしまわないデータの可視化
講師:草薙邦広(名古屋大学大学院生)
時間
- 15:40-17:10
会場
- 609室
概要
本ワークショップでは,卒業・修士論文を執筆する学部生・院生,または量的研究を今から始める研究者を対象として,以下の様なデータの可視化方法について幅広く紹介します。特にAPAスタイルに準拠した望ましい図の作成方法について,細かい部分に目を配りながら進行したいと思っています。
- きれいな折れ線グラフの描き方とエラーバーについて
- 箱ひげ図
- 蜂群図
- 散布図行列
- 重ねあわせヒストグラム
- 確率密度曲線による様々な可視化
配布資料
- www.slideshare.net
- sites.google.com
自由研究発表
第1室(ファカルティラウンジ)
①:13:00-13:30
日本人英語学習者の作文における誤りのアソシエーション分析
- 石井雄隆(早稲田大学大学院生)
発表概要
英語学習者が産出する誤りの共起に関する情報は、教室における作文指導などにおいても重要である。本研究ではKonan-JIEM Learner Corpusと呼ばれる日本人英語学習者が産出した英作文のエラータグ付きコーパスを用いて、作文における誤りのアソシエーション分析を行った。アソシエーション分析とは、百貨店や店舗で集めている購買履歴から顧客が購入するアイテムの組み合わせの規則を抽出するために用いられているものであり、外国語教育の文脈においては、小林 (2013)が、英語学習者の発話コーパスの分析に用いており、投野 (2013)では学習者のCEFRレベルの推定などで利用されている。本研究では、一つのエッセイ中にどういった誤りが共起するかをトピックごとに検討した。その結果、トピックによって学習者が共起して産出しやすい誤り、またトピックの影響を受けにくい誤りが観察された。
配布資料
- なし
②:13:40-14:10
語彙の豊かさ指標の信頼性・妥当性の基礎的検証:テキストの長さ・トピック・スタイルに焦点を当てて
- 石井卓巳(筑波大学大学院生)
発表概要
ライティング・スピーキング評価の観点の一つとして,語彙の豊かさ(lexical richness)の測定が挙げられる。語彙の豊かさは,学習者がどのくらい多様且つ広範な語彙を使用しているかを量的に示す指標であり,学習者の熟達度,アウトプットの質,受容語彙サイズ,産出語彙の語彙的発達に大きく寄与する。
しかしながら,語彙の豊かさ指標に関する先行研究において,信頼性・妥当性の検証が十分に行われているとは言い難い。信頼性・妥当性を欠いた指標を用いれば,研究の結果や解釈が誤った方向に進むおそれがあるため,その検証は極めて重要な課題である。
本発表では,語彙の豊かさ指標の先行研究における信頼性・妥当性の検証の実態と課題を概観した上で,語彙の豊かさ指標に関する信頼性・妥当性の基礎的検証の方向性を示す。また,基礎的検証に大きく関わるテキストの長さとトピック,併せて考慮すべきではないかと発表者が提案するテキストのスタイルの3種類の要因に焦点を当てる。
配布資料
- なし
③:14:20-14:50
WritingMaetriXと表計算ソフトを用いたライティングプロセスの分析方法
- 川口勇作(名古屋大学大学院生)
- 草薙邦広(名古屋大学大学院生)
発表概要
ライティングプロセス記録・分析ソフトウェアであるWritingMaetriX(以下WMX,草薙・阿部・福田・川口, 2013)では学習者のライティングにおけるキー入力およびその入力された時間を記録し,その記録されたキー入力を元に語数の時系列変化を棒グラフで図示したり,動画再生と同様の操作でライティングプロセスを再生したりすることが可能となる。ライティングの記録は拡張子が.klgのテキストファイルとして出力されるが,この.klgファイルはtxtファイルと同じタブ区切り構造でできており,一般的な表計算ソフトウェアで簡単に処理することが可能となっている。したがって本発表では,表計算ソフト(Microsoft Office Excel)とWMXによって出力された.klgファイルを用いたライティングプロセスの分析方法や,研究・教育実践において想定されるWMXの使用方法を報告する。
配布資料
- 配布資料はこちらからダウンロードできます。
第2室(609室)
①:13:00-13:30
タスクを用いた言語指導における実験心理学的研究と指導法効果研究の接点
- 福田純也(名古屋大学大学院生・日本学術振興会特別研究員)
発表概要
タスクを用いた言語指導は,第二言語習得の基盤的研究と,教授法研究の接点として注目を浴びており,これまでもその指導がもたらす介入効果の記述と説明が,第二言語習得研究の理論的,及び実証的な調査や実験的研究結果から試みられている。本発表は認知的相互作用主義(cognitive-interactionist)の視点に立ち,タスクを用いた言語指導研究における,実験心理学的アプローチによる一時的・短期的・横断的研究と,指導法の介入効果による学習者パフォーマンスの長期的変容を見る縦断的研究から得られる知見の接点を探る。そのために,これまでのタスク関連研究の流れと理論的背景,それらを踏まえた実証的研究を俯瞰した後,それぞれのアプローチから得られる知見の有用な点,ならびに限界点を指摘し,整理する。その整理に基づき,それぞれの研究から主張できること・できないことについて考察する。最後に,それまでの考察を以って,今後のタスクを用いた言語指導研究の実施に対する示唆と克服すべき問題点を提示する。
配布資料
- なし
②:13:40-14:10
発表キャンセル
③:14:20-14:50
英語学習者と母語話者の句構造頻度の比較
- 阿部大輔(名古屋大学大学院生)
発表概要
複数の語から成る表現の研究にはn-gramという単語の連鎖を見る手法が使われることがある。しかし、n-gramでは冠詞や前置詞で終わるような、構造的に完結していない表現を多く拾ってしまうため、研究の目的によっては理想的でないことがある。本研究では完全な構造の使用頻度を見るため、構文解析機を用いて学習者コーパスと、対応する母語話者の添削文に統語タグを付加した。そのタグに基づき作成した句構造の頻度情報を元に、コレスポンデンス分析を行った結果を報告する。
発表資料
- なし
第3室(623室)
①:13:00-13:30
英語圏への留学経験の有無と心理的欲求との関係:日本人英語学習者を対象に
- 神谷和孝(名古屋大学大学院生)
発表概要
本論文では、日本人英語学習者を対象に、「英語圏への留学経験がある学習者群(SA群)は、未経験学習者群(AH群)よりも、3つの心理的欲求の充足度は高くなるのか」を研究課題として設定し、調査を行った。この「心理的欲求」とは、英語学習に対して学習者が抱く情意面の欲求のことで、自律性、有能性、関係性の3欲求から成り立つ。研究参与者は、愛知県内の大学(院)にて英語を専攻する学生(英語圏へ8か月以上留学したSA群とAH群を60名ずつ、計120名)とした。また調査方法としては、廣森(2006)で使用されたアンケートなどを用いた。結果、有能性では両群間で有意差が見られたが、自律性と関係性では両群間で有意差が見られなかった。従って、英語圏へ留学をすることで、「英語ができるようになった」という欲求の充足感は高くなる一方、「主体的に英語学習に取り組んでいる」、または「他者と協力的に英語学習を行っている」といった気持ちの充足には、直接的には結びつかない可能性が高いことが明らかとなった。
配布資料
- なし
②:13:40-14:10
学習者コーパスNICEを用いた学習者の”of the”の使用に関する考察
- 後藤亜希(名古屋大学大学院生)
発表概要
英語母語話者コーパスにおいて、最も出現頻度の高い語はtheであり、次に高いのはofである。一方学習者コーパスでは、コーパスによってその出現頻度にばらつきがある。村尾(2013)は、学習者コーパスNICEの英語母語話者と日本人英語学習者(上級・中級)のデータにおいて、ofを含むlexical bundles(話し言葉や書き言葉で繰り返し共起する単語の連続)がどの程度使われているかを比較した。その結果、ofの使用頻度は、中級学習者、上級学習者、母語話者の順に増加することが示された。また、母語話者は学習者よりもofを含むlexical bundlesを多く使用するが、学習者間では差は示されなかった。
本研究では、村尾(2013)の追行研究として、ofと共に使用頻度が高いtheも対象とし、英語母語話者と日本人英語学習者のof theを含むlexical bundlesの使用頻度と、その用法の違いについて分析を行う。また、of the を含む高頻度のphrase-frameがどの程度使われているかを英語母語話者と日本人学習者間で比較する。
配布資料
- なし
③:14:20-14:50
- 平石順久(名古屋大学大学院生)
発表概要
英語は強勢拍リズムの言語といわれ,強強勢と強強勢の間のリズムのかたまりを1フットとみなし,強強勢間のリズムを同じにしようとする傾向があるといわれている。他方日本語はモーラ拍リズムの言語といわれ,2モーラを1フットとしてリズムを取る傾向があるといわれている。また,英語ではアクセントの要素として音の強さの他,母音の長さや基本周波数(F0)の高さなども影響してくるが,日本語では音の高低がアクセントとして用いられ,母音長や音の強さはほとんど意識されない。本研究では,北米へ9か月間交換留学生として滞在した日本語母語話者である大学生7名の英語発話における強勢パターンの変化を,母音長(duration),基本周波数(Fundamental frequency = F0),音の強さ(Intensity)の面から音響的に分析した。また留学経験による変化の特徴を考察するために留学前後に収録した文章音読発話を用い,さらに米国英語母語話者5名の音声と比較をした。
配布資料
- なし