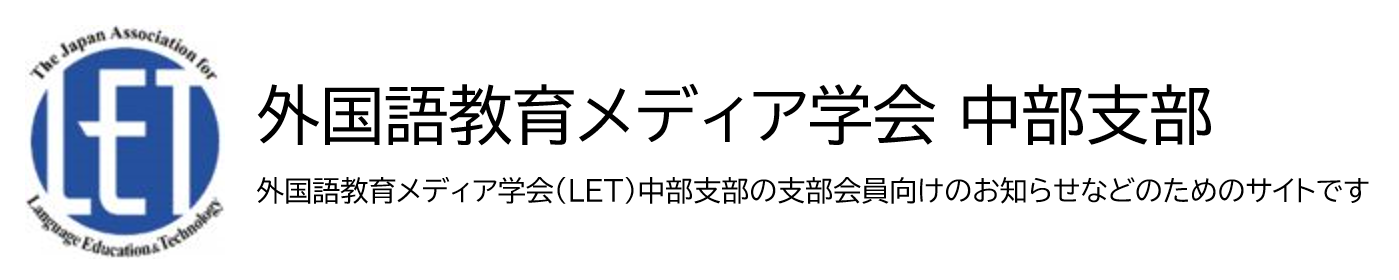卒論修論発表
会場:カンファレンスホール
① 13:05-13:35
TOEICリーディングセクションにおける読解力測定の妥当性
- 原和久(静岡大学学生)
発表種別
- 卒業論文
発表概要
今日、日本ではTOEICテストが英語能力を表す指標の一つになっている。主に就職活動の際にこのテストの点数がそれだけの英語能力を持ち合わせているかの基準とされているが、ほんとうにTOEICテストは受験者の英語能力を測定できているのか。本研究ではTOEICのリーディングセクションおける妥当性を読解力、語彙知識、和文英訳力の3つの相関関係などをもとに検証した。実験内容は大学生29人を対象に語彙テスト、読解テスト、和文英訳テストを受けてもらい、その得点から相関関係などを分析した。先行研究ではL2の読解力は語彙知識や文法知識などに大きな相関関係があるとされているにもかかわらず、結果として本研究ではあまり大きな相関関係が出なかったことから、TOEICのリーディングセクションは語彙知識あるいは和文英訳の能力以外の他の要素が得点に関係しているのではないかということが考察した。
配布資料
- なし
② 13:35-14:05
第二外国語としてのフランス語の綴りと発音に関するe-learning教材の開発とその効果:帰納的学習と演繹的学習の比較
- 熊崎美世(名古屋大学大学院生)
発表種別
- 修士論文発表
発表概要
本研究では,フランス語の学習経験がない日本語母語話者のための,フランス語の綴りの読み方を学ぶ教材を作成した。これは,帰納的学習法と演繹的学習法の2つの学習法を1つにまとめ,さらにその提示の順序を入れ替えた計2種類のものであった。実験ではその教材の学習効果を測るため,事前と事後,遅延テストを行い,既習語と未知語とに分けて,提示法,時間軸及び項目間の違いを比較した。その結果,本研究においては,教材による学習効果が少なからず得られたが,学習法(提示法)による差異は見受けられず,項目による差異が大きかったこと,学習した内容は未知語へも応用することができるということがわかった。また,アンケート調査により,実験へ参加したことでフランス語に興味を持つようになったことや,本研究で開発した教材に対して肯定的な評価がなされていたこと等がわかった。以上により,フランス語の綴りと発音を学習することには,意義があると考えられる。
配布資料
- なし
③ 14:05-14:35
中学校英語学習者における読解構成技能のプロファイリング:音韻認識・デコーディング・語彙サイズに焦点を当てて
- 栗田朱莉(名古屋大学大学院生)
発表種別
- 修士論文発表
発表概要
これまでの英語話者を対象にした研究からは,音韻認識は英語のデコーディング能力や読解能力との関連が強いことが明らかになっているが,どのレベルの音韻認識が必要かは研究によって議論が分かれている。また,第二言語においては高熟達度の学習者を対象とした研究はあるものの,初期の学習者を対象とした研究は限られている。 これらを踏まえ,本研究では初期の日本人英語学習者を対象に,日本語と英語で必要な音節・モーラ・音素レベルの音韻認識課題,デコーディング課題および語彙知識(語彙サイズ)課題を実施し,その特徴を探索的に調査した。それぞれの課題の成績を用いて混合分布モデルによる分析を行い,3つのグループに分類し,その特徴を記述することでプロファイリングを行った。結果,音素レベルの音韻認識のみが他のグループより著しく低いグループは,デコーディング課題と語彙サイズも低い成績を示した。このことから,音素レベルにおける音韻認識の低さと,デコーディングや語彙の習得困難性が結びついている可能性が示唆された。
配布資料
- なし
④ 14:35-15:05
外国語教育におけるe-ラーニングに関する一考察
- 中島敬之(京都大学大学院生)
- 壇辻正剛(京都大学)
発表種別
- 修士論文発表
発表概要
高等教育においてもe-ラーニングによる学習環境が急速に整いつつあるが、その特性はまだ十分に活かされていない。本稿の目的は、e-ラーニングをとりまく現状を分析し、その問題点及び次世代技術を視野に入れた展望の検討を行なうことで、将来の教育への示唆を得ることである。そこで、e-ラーニングの普及状況や外国語教育への利用について文献調査を行なうとともに、学生、教員へのアンケートによる意識調査を実施した。アンケートでは、e-ラーニングの利点の一つである音声教材の豊富さなどを学生は求めているが、教員は自律性が高く自身の負担を軽減できる教材を求めている等の意見の齟齬も認められた。さらに、e-ラーニングへの応用が期待されるヒューマンセンシング技術、特にKinectに着目し、応用事例の文献調査と、学習者の集中度や興味の度合いの自動判定について実際に検討を行ない、次世代の教材の可能性についても考察を行なった。
配布資料
一般研究発表
第1室(7Fカンファレンスホール・実証研究)
① 15:10-15:40
日本人英語学習者の音声言語の文処理におけるプロソディの影響:予備実験と今後の課題
- 後藤亜希(名古屋大学大学院生)
発表種別
- 一般研究発表
発表概要
プロソディ情報は,聞き手が統語構造を把握する際の手がかりになるといわれている。本研究は,文構造の違いにより,学習者の統語構造の把握のためのプロソディの使用には差がみられるのを明らかにすること目的とする。プロソディ情報のみの影響を測定するため,統語的一時曖昧文の一部を音声提示する手法を用いて日本語,を第一言語とする英語学習者(N = 25)を対象に予備実験を行った。統語的一時曖昧文として,後期閉鎖節/早期閉鎖節文のペア(k = 20),プロソディにより主語が異なる文ペア(k = 20)を用い,実験参与者は統語的一時曖昧文の一部が音声提示され,ペアのうちいずれの文が発話されているかを選択する課題が与えられた。結果,学習者は音声受容の早い段階でプロソディを用いて統語構造を予測することが示された。また,文構造により,プロソディの影響には差がみられることが示された。
配布資料
- なし
② 15:40-16:10
注意の量と焦点はどちらがより言語発達を予測するか
- 福田純也(名古屋大学大学院生・日本学術振興会)
発表種別
- 一般研究発表
発表概要
注意は第二言語の習得において重要な役割を担うとされている。先行研究ではその注意の「量(注意を向けた回数など)」を取り扱ったものと「焦点(特定の側面に対して注意を向けた割合)」を取り扱ったものがあるが,研究においてそのどちらかを取り扱う積極的な理由を論じているものはほとんどなく,概観の際においてもそれらは同様のものとして扱われている。そこで,本研究ではその注意の「量」と「焦点」のどちらがより言語発達に寄与するかを検討した。 実験には16人の大学生が参加した。参与者はエッセイライティングを行い,その後自由にそのエッセイを推敲してもらった。その際,修正を行った部分に対してなぜその修正を行ったのかに関して全ての箇所で言語化を求めた。その後,同じトピックで再度ライティングを行った。分析に際し,文法的な部分に言及した回数を「文法に対する注意の量」,すべての言及に対する文法的な言及の割合を「文法に対する注意の焦点」とし,数量化を行った。分析の結果として,注意の量は統語的複雑さを予測するが,注意の焦点はその予測力がない可能性が示唆された。
配布資料
- なし
③ 16:10-16:40
コンピュータ支援語学学習態度に性差は影響するか:多母集団の同時分析を用いて
- 川口勇作(名古屋大学大学院生)
発表種別
- 一般研究発表
発表概要
コンピュータ支援語学学習(CALL)に関する先行研究や経験的事実に基づく言説において,CALLに対する態度に男女差が存在するという主張が散見される。本研究では,性差が学習者のCALL態度に及ぼす影響を明らかにするため,構造方程式モデリングを用いた多母集団の同時分析を援用し,性別を要因とする分析を行った。CALL態度の測定には,信頼性・妥当性を備えた,コンピュータ支援語学学習態度尺度(川口・草薙, 2014)を用いた。多母集団の同時分析の結果,男女において同様の因子構造が再現され,男女間で因子平均の比較が可能であるという結果を得た。また,因子平均・分散・因子間相関の値を男女で比較した結果,CALL態度の下位概念ごとに男女間に差がみられ,またその差も下位概念ごとに異なる傾向を示した。これらの結果は,CALL態度の有り様に性差が影響を及ぼす可能性を示唆するものであった。
配布資料
- 発表資料はこちらからダウンロードできます。
第2室(6Fファカルティラウンジ・コーパス)
① 15:10-15:40
文法的誤りの頻度情報を用いた英語学習者のライティング評価の予測
- 石井雄隆(早稲田大学大学院生)
- 近藤悠介(早稲田大学)
発表種別
- 一般研究発表
発表概要
本研究では,日本人英語学習者のライティングにエラータグが付与されたKonan-JIEM Learner Corpus (Nagata, Whittaker, & Sheinman, 2011: KJLC)を用いて,文法的誤りの頻度からライティング評価の予測を試みた。KJLCは10個のトピックを含んでいるが,本研究では,各トピックの文法的誤りの頻度を基にクラスタリングし,この頻度の類似度が高い5つのトピックを対象とした。基準変数は,成田(2013)で優れていると評価されたものを1,そうでないものを0とした2値データを用いた。またKJLCでは20種類のエラータグが付与されているが,成田による評価の2つのカテゴリーで平均値が大きく異なる10個のエラータグの頻度を開平変換し,予測変数とした。標準ユークリッド距離を用いた近傍法を使用し,評価データにおいて,本予測方法を用いて算出した評価と成田による評価のカッパ係数は.57であった。今回の結果から,文法的誤りの頻度のみを用いても,学習者のライティング評価は,高い精度で予測できることが示唆された。
配布資料
- なし
② 15:40-16:10
可算性の曖昧さは数の一致の誤りを誘発しやすいか:学習者コーパスを用いた予備的調査
- 田村祐(名古屋大学大学院生)
発表種別
- 一般研究発表
発表概要
本研究は,学習者コーパスのライティングデータを分析の対象とし,学習者の産出する 名詞句内の数の一致の誤りの言語的要因を検討したものである。学習者コーパスNICE2.2.1を用いて、指定詞の種類が数の一致の誤りに影響を与えるかを調査した。all, many, some, these, thoseを含む表現を抽出し、チャンクとして処理されているものを除外し分析を行った。結果、指定詞の種類の影響はみられなかったものの、指定詞と名詞句の主要部の線的距離や名詞の特性の影響があることが示唆された。
配布資料
- なし
③ 16:10-16:40
なし
第3室(7F 705室・実践報告)
① 15:10-15:40
なし
② 15:40-16:10
Efficacy of Processing Level in Vocabulary Acquisition: The Relation between Context and Vocabulary Depth
- 肥田依己子(名古屋大学大学院生)
- HIDA, Emiko Graduate Student, Nagoya University
発表種別
- 一般研究発表
発表概要
This study explores the efficacy of processing level in vocabulary acquisition and examines the relation between use of context and vocabulary depth (i.e., producing translation and sentences of polysemous words). Although learning the same new words in different situations may seem to have the same process, a learner’s efficacy in each task is not identical because of processing level. Three vocabulary learning tasks that require different processing levels were provided in the present study. It is predicted that the retention scores of the target words will be highest in a task requiring deep processing. The result and effects on each task will be discussed in light of processing level and two different types of context (i.e., given context and generated context) in the presentation.
配布資料
- なし
③ 16:10-16:40
中学校段階におけるスピーチ指導のあり方:協同学習とプロセスライティングに着目して
- 山田慶太(名古屋市立守山東中学校)
発表種別
- 一般研究発表
発表概要
本実践は筆者が平成25年度公立中学校2年生3クラス120名の生徒を対象に行ったものである。タスクとして設定したのは”My Precious Moment”または”My Favorite Thing”をテーマとしたスピーチ発表である。スピーチ原稿作成から口頭発表までをプロジェクトとし,検定教科書を用いた指導と平行しながら1月~3月までの約3ヶ月間週4時間のうちの1時間を割り当て継続的に取り組ませた。1人の教師が1クラス40名の生徒に効率よくスピーチ原稿作成、発表等の指導する上で、協同学習とプロセスライティングの手法を取り入れることの有効性について、具体的な指導手順、生徒が作成した発表原稿、口頭発表の様子、振り返りの様子などをもとに紹介したいと考える。
配布資料
- なし
第4室(6F 623室・テクニカルレポート)
① 15:10-15:40
なし
② 15:40-16:10
外国語教育研究におけるメタ知識基準の応用可能性:明示的および暗示的知識を測定するために
- 草薙邦広(名古屋大学大学院生・日本学術振興会)
発表種別
- 一般研究発表
発表概要
認知心理学における人工言語学習(Artificial Grammar Learning;AGL)の分野では,無意識化における知識の創発(無意識的学習)が重要な研究テーマである。近年のAGL研究は,無意識的学習の結果として得られる暗示的知識(implicit knowledge)を測定するために,メタ知識基準(metaknowledge criteria)とよばれる指標を頻繁に援用している。本発表では,このメタ知識基準についての手法上の検討をおこなうとともに,実際の外国語教育研究データをもちいて,当手法における外国語教育研究への応用可能性を探る。 具体的には,まず,AGL研究における重要な諸概念:(a)構造知識(structural knowledge),(b)判断知識(judgment knowledge),(c)当て推量基準(guessing criteria),(d)メタ知識基準,(e)信号検出理論,を概観する。その後,さまざまなメタ知識基準値の計算方法を紹介し,そのなかでも,meta-d’,テトラコリック相関係数,Cochran–Mantel–Haenszel法,および調整変数分析(moderator analysis)が手法的有用性をもつことを示す。最後に,外国語教育研究におけるメタ知識基準の位置づけに関する試案を述べる。
配布資料
- なし
③ 16:10-16:40
テキスト分析のブラックボックス化を防ぐために:英文解析プログラムと学習者コーパスを例に
- 石井卓巳(筑波大学大学院生)
発表種別
- 一般研究発表
発表概要
テキスト分析は,第二言語習得学や英語教育学の分野において,教材開発におけるテキストの難易度の調査や,学習者の産出したアウトプットにおける言語的発達の研究などのために行われてきた。最近では,大規模なデータを収集したコーパスと呼ばれるデータベースや,テキストの表層的特徴に関する従来の指標だけでなく意味,談話,結束性,一貫性等の側面に関する指標も簡易に算出できる英文解析プログラムも,テキスト分析の際に利用可能である。しかしながら,そのような英文解析プログラムやコーパスは,テキスト分析のブラックボックス化を招くおそれがあり,利用には注意が必要である。そこで本発表では,テキスト分析に利用される英文解析プログラムと学習者コーパスを例に,テキスト分析のブラックボックス化を論じると共に,そのブラックボックス化を防ぐ方法について提案や議論を行いたい。
配布資料
- なし
基調講演
CALL研究を考える:ひと・もの・ことの視点から
- 住政二郎(流通科学大学)
- 16:45-17:45
講演概要
本発表は3つのパートからなる。最初に,CALL研究を「ひと・もの・こと」の3点から捉え直すエコロジカル・パースペクティブについて紹介する。次に,その具体例として,発表者が現在取り組んでいる,多段階反応モデルを活用した学習支援システムの開発と実践への応用について紹介する。多段階反応モデルとは,多値データを取り扱うために,2パラメーターロジスティックモデルを拡張したものである。一般的なCATは,習熟度に応じて適切な項目を受験者に提示することができる。しかし,回答が誤答であった場合,なぜ誤答であったのかという情報を受験者に提示することができず,受験者は学習を深めることができない。そこで,多段階反応モデルを活用し,項目応答理論の原理を足場掛けの仕組みとして応用することで,受験者の習熟度に応じて適切な問題項目とヒントを提示するシステムの開発に取り組んでいる。発表の最後には,院生を中心とするこの部会の参加者に考えてもらいたい話題についても触れる。
資料
- なし