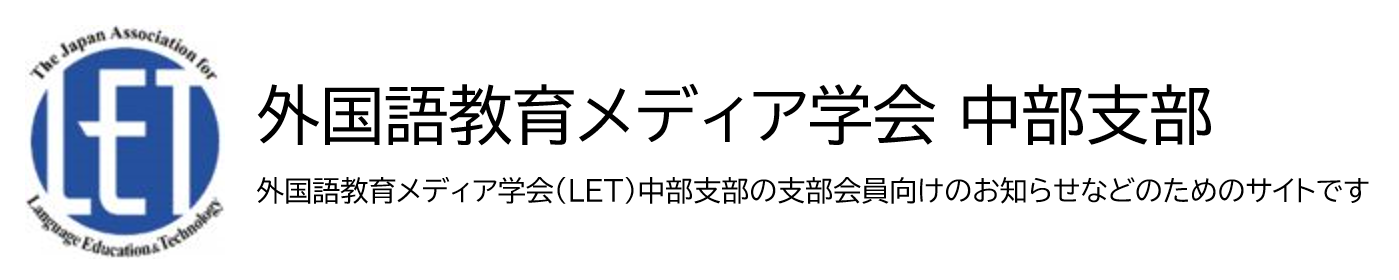一般研究発表
第1室(516室)
① 10:40-11:10
L2ライティングにおける統語的複雑さ指標の選択:構成概念妥当性の観点から
- 西村嘉人(名古屋大学大学院生)
発表概要
本発表では,ライティングにおける統語的複雑さの概念に焦点を当て,それを測定する際に用いられる指標の妥当性を検証することを目的とする。これまで用いられてきた代表的な指標は,その指標が適切に学習者の能力を測定出来ているかという構成概念妥当性の観点からはあまり検証されておらず,学習者の習熟度との相関の強さという観点から指標を選択していたに過ぎない。そこで本発表では,大規模な学習者コーパスをもとに,階層的な構成概念モデルに基づいて,これまで使用されてきた統語的複雑さの指標値を対象に偏相関係数を算出し,指標の妥当性について検証する。学習者コーパスは,International Corpus of Learner English Version 2を用いた。指標値の算出には,L2 Syntactic Complexity Analyzerを用いた。算出した指標値をもとに,階層的統語的複雑さの枠組みに則り,構成概念妥当性の観点から妥当性のある指標の提案行う。また,統語的複雑さという構成概念についても議論する。
配布資料
- なし
② 11:15-11:45
文法性判断課題における反応時間と主観的測度は正答率を予測するか:文法項目の違いに焦点をあてて
- 田村祐(名古屋大学大学院生)
発表概要
本研究では,文法性判断課題における反応時間と主観的測度が正答率を予測するかを,普通名詞と物質名詞という2つの言語項目を用いて検証した。Tamura and Kusanagi (2015)では文法性判断課題での回答の時間を操作することによって明示的知識・暗示的知識を操作的に定義したが,Tamura et al. (in press)では,スピード軸だけでなく意識軸を考慮にいれ,その2軸の斜行性を考慮する必要性を明らかにした。本研究では,この観点を取り入れ,反応時間と主観的測度と正答率の関係を議論する。文法性判断の後に,「自分の知っている規則で説明できるか」または「直感であるか」の判断を求める文法性判断課題を日本人大学生24名を対象に行い,一般化線形混合モデルを用いて分析を行った。結果として,(a)普通名詞に関しては意識的な知識を持っているが,それらは必ずしも遅いとは限らないこと,(b)物質名詞に関しては意識的な知識も無意識な知識も持っていなかったこと,の2点が明らかになった。
配布資料
- 投影資料:http://www.slideshare.net/yutamura1/ss-58753238
- 配布資料:https://drive.google.com/file/d/0BzA9X1kZX185Nk5ONDJ5eUlOLVk/view
第2室(517室)
① 10:40-11:10
外国語教育研究における再現可能性と文芸的プログラミングのすすめ
- 草薙邦広(名古屋大学大学院生・日本学術振興会特別研究員)
発表概要
我が国において,科学的手法(scientific method)による外国語教育研究は,長く見積もっても半世紀程度の歴史ももたない比較的若い研究分野であり,特にデータ分析に関わる統計手法の選択,データ収集方法のデザイン,結果の報告,そしてその解釈について,関連分野と比しても決して高い水準にあるとはいえない。特に近年は,さまざまな社会的な要因によって,外国語教育研究の質,とりわけ,再現可能性(reproducibility)に関する研究者の意識が高くなりつつある。そこで,本発表では,外国語教育研究における再現可能性の問題を指摘した上で,近年注目を浴びている再現可能な研究(reproducible research, RR)および,それを可能にする文芸的プログラミング(literate programming)について紹介し,今後の研究方法論に関する展望を述べる。
配布資料
- なし
② 11:15-11:45
ラーニング・コモンズの外国語教育への応用
- 中島敬之(京都大学大学院生)
- 南條浩輝(京都大学)
- 壇辻正剛(京都大学)
発表概要
我々は京都大学学術情報メディアセンター内において,少人数スペースで日本人大学生と留学生とが交流しながら外国語学習を行う「ランゲージ・コモンズ」を展開している。学習テーマの1つに「海外留学や海外移住などを行った際に支障となる文化差による壁を克服するために,実際に留学生の母国の文化や教育環境など,日本にいてはなかなか耳にすることのできない生の声を聞き,外国語学習と留学・渡航準備ができること」を掲げている。「日本文化を外国語で発信する内容のデジタル語学教材」を用いることで,単なる外国語の学習に留まらない学び,すなわち日本人学生が外国語学習を行うだけでなく,日本文化を学ぶという点から留学生にとっても学びを生み出し,学び合いを可能とする環境を提供している。これにより大学における外国語教員の指導などに活かすことが出来ることが考えられ,学生が能動的に学修に取り組むアクティブ・ラーニングの教育面からの有用性も期待できる。
配布資料
- なし
基調講演
否定フィードバックの言い直し(recasts)について考える
- 酒井英樹(信州大学)
講演概要
言い直し(recasts)は、第二言語習得研究において最も多くの焦点があてられてきた否定フィードバックの1つです。また、教育的にも、Focus on Formを促進する1つの手段として注目されてきました。なぜ、第二言語習得研究者は、言い直しに注目してきたのでしょうか。言い直しは教育的に効果があるのでしょうか。また、言い直しをどのように与えていけば良いのでしょうか。本講演では、私が行ってきた研究を紹介しながら、(1) 言い直しの役割と意義、(2) 言い直しに関する研究の経緯、(3) 言い直しに関する教育的示唆、(4) 今後の方向性について、考えていきます。